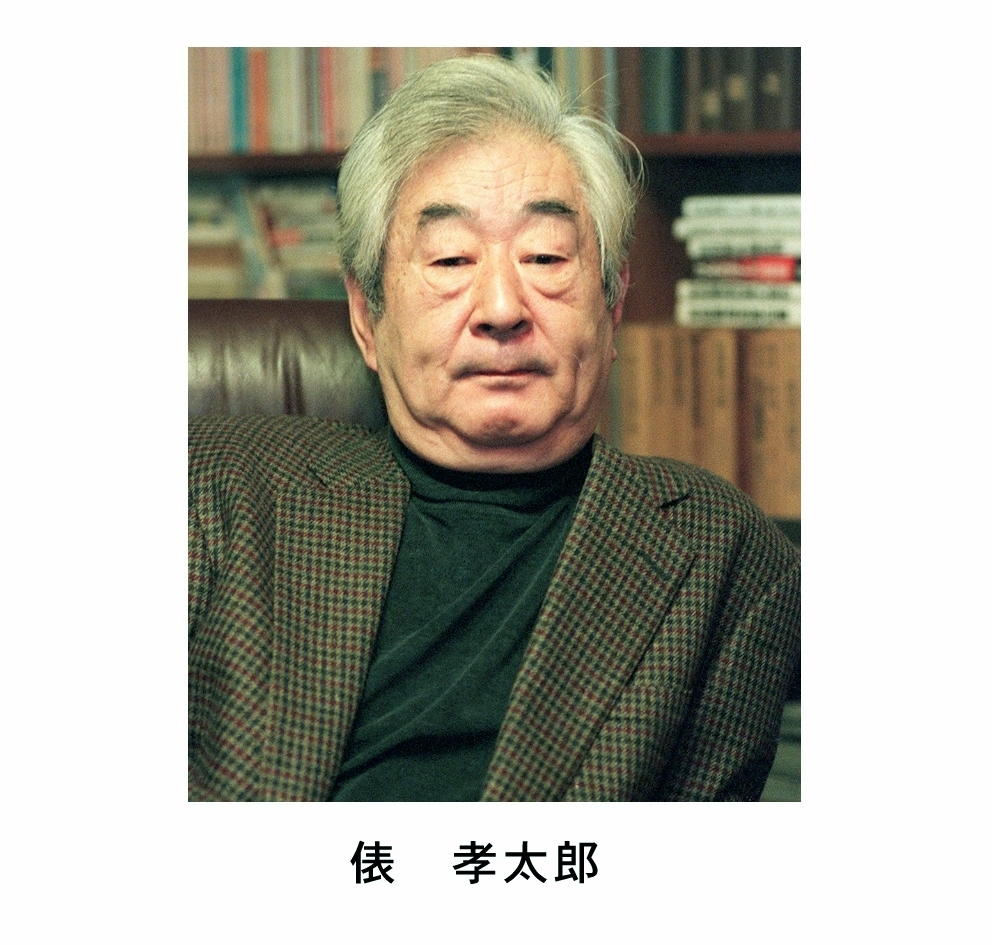30人の名監督、それぞれを代表する30本の最高傑作
フランシス・フォード・コッポラのベスト、タランティーノの最高傑作、あるいはキャスリン・ビグローの最上の一本、スピルバーグの作品を一つだけ選ぶなら? 各監督の知られざる名作に注目しながら最高の一本をご紹介しよう。
1912年、処女航海のさなか氷山にぶつかり、北大西洋に沈んだタイタニック号。その悲劇の豪華客船を舞台に、一生に一度の恋愛を描く、あまりにも有名な映画が『タイタニック』である。セリーヌ・ディオンの歌声が聞こえてくるようだ。 ジェームズ・キャメロン監督作には他にも、『ターミネーター』シリーズや『アバター』シリーズがある。
コーエン兄弟こと、ジョエル・コーエンとイーサン・コーエン。彼らは実の兄弟で、共同で映画制作を行なっている。ジェフ・ブリッジスの名演が光る『ビッグ・リボウスキ』は、シュールでサイケなボウリング映画で、コーエン節が100パーセント炸裂している。代表作には他に、『ファーゴ』『トゥルー・グリット』や、愛すべき『インサイド・ルーウィン・デイヴィス 名もなき男の歌』などがある。
ソフィア・コッポラといえば『ロスト・イン・トランスレーション』が一番という人もいるだろうし、『マリー・アントワネット』を推す向きもある。だが、初監督作である『ヴァージン・スーサイズ』をしのぐほど豊かなポエジーをたたえた作品は(もちろん他の作品もそれぞれに素晴らしいのだが)いまだ現れていないと言える。
キャスリン・ビグローの代表作といえば、『デトロイト』や『ゼロ・ダーク・サーティ』といったタイトルが思い浮かぶかもしれない。だがここでは、サーフィンをからめたクライム・アクション『ハートブルー』(1991年)を推したい。キアヌ・リーヴスが素晴らしいし、全盛期のパトリック・スウェイジも堪能できる。サウンドトラックにはメジャーデビュー前のシェリル・クロウの楽曲が収録されている。
メキシコシティで生まれ育ったアルフォンソ・キュアロン。『天国の口、終りの楽園。』や『トゥモロー・ワールド』の評価も高い。だが2018年に公開された『ROMA/ローマ』の映像美たるやすさまじく、現時点での最高傑作としたい。
ニュージーランド出身の監督ジェーン・カンピオンの『ピアノ・レッスン』は文句のつけようのない傑作で、1994年のアカデミー賞では3部門で受賞を果たした。マイケル・ナイマンが手がけた印象的なサウンドトラックも忘れがたい。主演はホリー・ハンター、ハーヴェイ・カイテル。
『グッドフェローズ』『タクシードライバー』『ウルフ・オブ・ウォールストリート』、その他多数。マーティン・スコセッシ映画は傑作ぞろいだ。今回チョイスする『ギャング・オブ・ニューヨーク』は、タイトルの通りギャングたちの抗争を描き、現代のニューヨーク、ひいてはアメリカ社会の成り立ちを明らかにしていく作品である。主演のレオナルド・ディカプリオもさることながら、ダニエル・デイ=ルイスが特にすばらしい。
2012年に亡くなったノーラ・エフロンは、ロマンティック・コメディの名人だった。その冴えた手腕は『恋人たちの予感』や『ユー・ガット・メール』、そして1998年公開の『めぐり逢えたら』で味わうことができる。トム・ハンクスとメグ・ライアンが演じる運命的な出逢いの物語は、人々の心をときめかせ続けている。
『レザボア・ドッグス』や『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』といった傑作もあるが、『パルプ・フィクション』こそクエンティン・タランティーノ映画の本質、その最良の部分を凝縮した作品といえよう。とにかく有名な映画でもあり、サミュエル・L・ジャクソンやブルース・ウィリス、ユマ・サーマンやジョン・トラボルタ、マリア・デ・メディロスといった出演者たちの演技が印象的である。
スティーヴン・スピルバーグの作品は、あまり深く考えずすべて傑作と言いたくなる。 だがあえて1本選ぶなら、『シンドラーのリスト』はどうだろう。映画としての出来はもちろん、ナチスによるユダヤ人大量虐殺を描いたこの作品の、特有の重みは見逃せない。
グレタ・ガーウィグは、最近では『バービー』『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』の監督として知られる。2017年の映画『レディ・バード』の主演をつとめるシアーシャ・ローナンはグレタ・ガーウィグの分身であり、思春期の凜とした、しかし揺れ動く心を余さず伝えている。
『ゴッドファーザー PART II』は、シリーズ第一作をしのぐ傑作として広く認められている。『地獄の黙示録』も大作だが、やはりゴッドファーザーのほうに軍配があがるだろう。シェイクスピア劇を思わせる見事な作劇である。
ヌーヴェルバーグの偉大な女性監督、アニエス・ヴァルダは2019年に90歳で亡くなった。彼女が監督と脚本を担当した1962年の映画『5時から7時までのクレオ』は、クレオという名の若い女性が主人公のモノクロ映画。クレオは午後7時に医者と会う約束があり、癌かどうかの検査結果を言い渡されることになっている。それまでの時間をつぶすために、彼女はパリの街をさまよう。
クリストファー・ノーラン、その長編映画監督デビューは1998年の『フォロウィング』だった。練りに練った壮大な脚本とケレン味のある映像には固定ファンがつき、いまや世界で最も有名な監督の一人になっている。最近の収穫として思い浮かぶのは『ダンケルク』や『インターステラー』『TENET テネット』(そして『オッペンハイマー』)だが、ここは初期の傑作『メメント』を推したい。公開当時、脚本の完成度の高さにみな舌を巻き、まさしく天才が現れたという悦びがあった。
2001年制作の『モンスーン・ウェディング』はおそらく、ミーラー・ナーイルの最高傑作だろう。彼女はインド出身の映画監督で、他の代表作には『その名にちなんで』やオムニバス映画『ニューヨーク、アイラブユー』の一編「宝石商と宗教」がある。
詩的で残酷な傑作、『オールド・ボーイ』(2003年)。バイオレンス映画の一つの到達点といえる。パク・チャヌク監督の復讐三部作の第二作(他は『復讐者に憐れみを』と『親切なクムジャさん』)にあたり、映画史における準古典になりつつある作品だ。
河瀨直美は世界的な評価が高い監督である。奈良県出身。尾野真千子のデビュー作となった『萌の朱雀』(1997年)も魅力的だが、ここでは晩年の樹木希林が主演をつとめた『あん』(2015年)を最高傑作に選びたい。
デンゼル・ワシントン主演、銀行強盗グループとの緊迫した頭脳戦を描く映画が『インサイド・マン』である。『ドゥ・ザ・ライト・シング』や『マルコムX』よりも政治色は控えめだが、映画の面白さをぞんぶんに引き出した質の高い作品に仕上がっている。
中国出身の若き映像作家、クロエ・ジャオは、『ノマドランド』や『エターナルズ』の監督として有名である。だが、ここでは長編第二作の『ザ・ライダー』を最高傑作に推したい。カウボーイ文化を題材にした本作は、ロデオで生計を立てる青年の人生を追う。現代の西部劇という点では、アン・リー監督の『ブロークバック・マウンテン』と共通するところもあるだろう。
ペドロ・アルモドバル監督の『神経衰弱ぎりぎりの女たち』は、カラフルで笑いに満ちたコメディ映画で、1988年の公開当時すぐれて前衛的な作品だった。現在では他のアルモドバル作品、たとえば『オール・アバウト・マイ・マザー』や『トーク・トゥ・ハー』と並び、その充実したフィルモグラフィーの中で異彩を放つ名作となっている。
ウディ・アレンの映画は、『アニー・ホール』『マンハッタン』『カメレオンマン』『マッチポイント』などなど、平均点が高い印象がある。総じてクオリティが安定したウディ・アレン作品の中で、今回はやや渋いかもしれないが『ウディ・アレンの重罪と軽罪』をチョイスしたい。おかしさと哀しみ、そして恐ろしさが同居するストーリーだ。
イザベル・コイシェはスペイン出身の映画監督。『死ぬまでにしたい10のこと』や『マイ・ブックショップ』などの優れた映画で知られている。サラ・ポーリーとティム・ロビンスが主演をつとめた『あなたになら言える秘密のこと』は、孤独な居場所を求める人々の物語。映像には冷やりとした感触があるが、イサベル・コイシェ作品のなかで最も熱く、エモーショナルな一本になっている。
ギレルモ・デル・トロはメキシコ出身の映画監督。2017年の『シェイプ・オブ・ウォーター』はアカデミー賞を4部門で受賞した。彼のキャリアの一つの到達点といえる作品で、ファンタジーの要素が混じった恋愛映画である。主演をつとめたのはイギリスの俳優サリー・ホーキンス。顔立ちがどことなく杉村春子に似ているような、とても繊細で個性的な役者だ。
フランス生まれのジュリー・デルピーは、『ビフォア・サンセット』(リチャード・リンクレイター監督作)などのヒロイン役で広く知られる。1969年生まれ。とても知性的な役者で、脚本や監督もこなす。2011年公開の映画『スカイラブ』は、ブルターニュ地方で一家で過ごす1979年のバカンスを描いている。ノスタルジックでほっこりする作品。
フアン・ホセ・カンパネラはアルゼンチン出身の映画監督。1959年生まれ。彼の最高傑作『瞳の奥の秘密』は、のちにハリウッドで『シークレット・アイズ』としてリメイクされた(主演はキウェテル・イジョフォー、ニコール・キッドマン、ジュリア・ロバーツ)。代表作には他に、『El mismo amor, la misma lluvia(同じ恋、同じ雨)』(1999年)、『El hijo de la novia(新婦の息子)』(2001年)、『Luna de Avellaneda(アヴェジャネーダの月)』(2004年)がある。
『ビフォア・サンライズ 恋人までの距離』『ビフォア・サンセット』『ビフォア・ミッドナイト』の「ビフォア」三部作のうち、シリーズ二本目の『ビフォア・サンセット』(2004年)がおそらく最も優れているのではあるまいか。旅先の車中で偶然出会い、どこまでもロマンティックに別れた二人。そんな彼らの9年後の再会を描くストーリーである。現実世界の時間を物語の時間にリンクさせる手法は、のちに『6才のボクが、大人になるまで』(2014年)で一つの完成を見る。
ドイツ生まれの若い女性監督、マーレン・アデ監督の『ありがとう、トニ・エルドマン』は、いちおうコメディではあるがジャンルに収まらない自由さで、2016年のカンヌ映画祭をあっと驚かせた。この映画については好きになるか、それとも肌に合わないかのどちらかにはっきりと分かれるだろう。
『愛、アムール』(2012年)は、ミヒャエル・ハネケの監督作で最も感動的な一本である。ジャン=ルイ・トランティニャンとエマニュエル・リヴァという高齢の役者、往年のベテラン役者が夫婦役を演じている。妻の認知症が進行し、夫が妻を介護するというストーリーだ。結末はけっして晴れやかではないが、そこに愛の純粋な形を見る人も少なくない。ミヒャエル・ハネケは観る者の心をざわつかせる映画を撮ることを得意としており、代表作に『ファニー・ゲーム』や『ピアニスト』がある。
映画界の生きる伝説、クリント・イーストウッド。『許されざる者』や『ミスティック・リバー』『マディソン郡の橋』『パーフェクト・ワールド』『ペイルライダー』などなど、数多くの名作を世に送り出している。ここでは彼の最高傑作として、『グラン・トリノ』をあげたい。玄関ポーチにどっかと腰を下ろし、缶ビール(労働者向けの安価な銘柄)を一本、また一本と空けていく頑固一徹なクリント・イーストウッド。それを見るだけでも観る価値がある。